スマホで簡単セルフチェック&夏に効く漢方処方5選
暑さ・湿気・夏バテ対策に効く処方と、毎日できる養生法を徹底解説
日本の蒸し暑い夏は、外気の「暑邪(しょじゃ)」と体内の「湿邪(しつじゃ)」が複合的に襲い、熱中症・夏バテ・食欲不振・むくみ・だるさを引き起こしやすい季節です。漢方ではこれらをまとめて「暑湿(しょしつ)」と呼び、体への負担を和らげる処方(方剤)や食養生があります。
本記事では、
- 夏養生の基本原則
- 代表的な夏処方の詳しい解説
- 毎日取り入れたい食養生&生活習慣
- 安全に使うための注意点
に分けて、30代女性の皆さんが実践しやすいレシピやコツをお伝えします。
1. 夏の漢方養生の基本原則

漢方の夏養生は、大きく3つの働きに分かれます。
- 清暑(せいしょ)
体内にこもった余分な「熱」を下げる働きです。夏の高温に晒された身体を内側から冷まし、発汗過多で失われた津液(体液)を補う処方を選びます。 - 利湿(りしつ)
蒸し暑さや水分摂取過多で生じる「湿気」を排出し、水分代謝を改善。むくみやだるさ、胃腸の不調を和らげます。 - 益気(えっき)
夏バテで消耗した「気」を補い、疲労回復や免疫力アップをサポート。疲れやすい、食欲が落ちた、動悸がする‥‥という方におすすめです。
漢方ではさらに、一人ひとりの 「証(しょう)」=体質や主訴に合わせて処方を使い分けます。無理せずセルフチェックし、適切な漢方薬を生活に取り入れましょう。
2. 【体質診断】まずはあなたの“証(しょう)”をチェック
漢方では、同じ夏バテでも体質により対策が異なります。以下の5タイプセルフチェックで、あなたの体質を見つけましょう。
| 質問項目 | 陽虚型 | 陰虚型 | 気滞型 | 瘀血型 | 湿熱型 |
|---|---|---|---|---|---|
| □ 冷房下で手足が冷えてつらい | ✔️ | ||||
| □ のぼせ・寝汗・口渇を感じる | ✔️ | ||||
| □ イライラ・胸の張り・ゲップが多い | ✔️ | ||||
| □ 生理痛・肩こり・肌のくすみが気になる | ✔️ | ||||
| □ 顔や体がベタつき、湿疹が出やすい | ✔️ |
- チェック数が最も多い列が主タイプです。
- 同数の場合は、両方の養生法を組み合わせましょう。
3. 各タイプの特徴&夏の養生法
3-1. 陽虚型(ようきょがた)
症状例
手足冷え、疲労感、食欲不振、むくみ
漢方処方
・苓姜朮甘湯…むくみ除去+温裏作用
・補中益気湯…気を補い、冷えた内臓を温める
夏の養生ポイント
・温性食材(山芋、生姜)を毎朝の薬膳粥に。
・冷房環境ではお腹にカイロ or ベルトを。
・朝食はぬるめの白湯で胃腸を目覚めさせる。
3-2. 陰虚型(いんきょがた)
症状例
のぼせ、寝汗、口渇、ドライ肌
漢方処方
・竹葉石膏湯…生津作用で潤い補給
・滋陰降火湯…陰を補いながら過剰熱を鎮める
夏の養生ポイント
・涼性食材(梨、トマト、きゅうり)を常温で。
・就寝前の寝汗対策に竹葉石膏湯を。
・メイク前にミスト化粧水で乾燥防止。
3-3. 気滞型(きたいがた)
症状例
胸やけ、イライラ、ゲップ、お腹張り
漢方処方
・加味逍遙散…疏肝理気+補血でストレス緩和
・柴胡桂枝湯…熱と寒を同時調整
夏の養生ポイント
・香り食材(ミント、陳皮)で気を巡らせる。
・深呼吸・軽いストレッチでストレス発散。
・食後のハーブティータイムを習慣化。
3-4. 瘀血型(おけつがた)
症状例
生理痛、肩こり、シミ・くすみ、冷え
漢方処方
・桂枝茯苓丸…活血化瘀で血流改善
・桃核承気湯…瀉下作用で瘀血を一掃
夏の養生ポイント
・黒ゴマ・黒豆入りの薬膳サラダで補血。
・軽いウォーキングで血行促進。
・お風呂は38~40℃で半身浴10分程度。
3-5. 湿熱型(しつねつがた)
症状例
ニキビ、湿疹、下痢傾向、口臭
漢方処方
・黄連解毒湯…清熱解毒で湿熱を排除
・八正散…利水清熱で膀胱部の湿熱除去
夏の養生ポイント
・苦味食材(ゴーヤ、緑茶)で清熱利湿。
・シャワー後はドライヤーで全身をしっかり乾かす。
・水分補給は室温のほうじ茶や水分補給用漢方茶。
4. 夏に必要な漢方おすすめ5選
以下の5処方は、いずれも夏にこそ選びたいものばかり。歴史的背景や代表的な生薬の役割も交えて詳しく解説します。
4-1. 清暑益気湯(せいしょえっきとう)
- 適応:重度の夏バテ、著しい倦怠感、脱力感、食欲不振
- 歴史:清の時代に医師・劉完素が「暑中益気湯」として著書に記載。
- 構成生薬:黄耆(おうぎ)4、白朮(びゃくじゅつ)3、人参(にんじん)3、茯苓(ぶくりょう)3、大棗(たいそう)2、甘草(かんぞう)1…計10種
- 黃耆…気を補う主薬
- 白朮・人参…中焦(胃腸)の働きを整える
- 生姜・大棗…滋養と補気をサポート
- 飲み方のコツ:
- 量:1日3包を、朝夕のほか昼食後にも。
- タイミング:食間(食後1時間~次食前)に、ぬるめの白湯100mlと一緒に。
- イメージ:外でのレジャー後や、連日の残業続きで体が抜け殻のように疲れているときに。
- ケース例: 社内イベントの熱中症予防に、朝夕と昼休みに清暑益気湯を服用し、午後のパフォーマンスが維持できた。
4-2. 五苓散(ごれいさん)
- 適応:むくみ、のぼせ、めまい、頭重感、二日酔い
- 構成生薬:茯苓(ぶくりょう)、猪苓(ちょれい)、沢瀉(たくしゃ)、蒼朮(そうじゅつ)、桂皮(けいひ)
- 茯苓・猪苓…利水(不要な水分排出)
- 沢瀉…尿量を増やす
- 桂皮…気を巡らせてのぼせを改善
- 飲み方のコツ:
- 量:1日3回、1包ずつ。
- タイミング:むくみを感じたタイミング—昼食後や帰宅後のリセットに。
- ワンポイント:
- 客先訪問の前や、長時間同じ姿勢で座り続ける日には、早めに五苓散で「水はけ」を良くしましょう。
4-3. 小建中湯(しょうけんちゅうとう)
- 適応:胃腸虚弱による腹痛・下痢、冷え、疲労
- 背景:宋の時代、傷寒論に登場する「建中湯」から派生。現代では胃腸温裏(おんり)と気の流れを整える処方として使われる。
- 構成生薬:桂枝(けいし)、人参、白朮、生姜、大棗、甘草…計7種
- 桂枝・生姜…胃を温める温裏作用
- 人参・白朮…脾胃を補う補中益気作用
- 飲み方のコツ:
- 量:1日3~4包。
- タイミング:冷房で冷えた夜や、下腹部の張りを感じたときに。
- プラスα:同量の生姜湯で溶くと温め効果アップ。
- 活用例: 冷房の効いたオフィスで昼食に下痢しやすい体質の方が、小建中湯で午後の集中力をキープ。
4-4. 黄連解毒湯(おうれんげどくとう)
- 適応:高熱、口内炎、ニキビ、イライラ、炎症性ののぼせ
- 構成生薬:黄連、黄芩、黄柏、梔子…計4種の“黄連三黄(さんおう)+梔子(しし)”
- 強力な 清熱解毒 作用で、火照りや炎症を鎮める。
- 飲み方のコツ:
- 量:1日3回、食後に。
- 注意:空腹時は胃腸に刺激があるため必ず食後服用。
- 使用場面: 夏フェス後のニキビ悪化や、冷房+冷たい飲み物でのどが痛むときの応急処置に。
4-5. 竹葉石膏湯(ちくようせっこうとう)
- 適応:のどの渇き、口渇、微熱、夜間の寝汗
- 構成生薬:竹葉(ちくよう)、石膏(せっこう)、人参、半夏、大棗、甘草…計6種
- 竹葉・石膏… 生津作用 で体内の潤いを補い、乾燥を和らげる。
- 飲み方のコツ:
- 量:1日2回、朝と就寝前。
- 効果UP:常温の水で溶いてゆっくり飲むとしみ渡るように潤います。
- 活用例: 就寝中の寝汗で朝起きると喉がガラガラ…という方におすすめ。
5. 安全に使うための注意事項
- 医師・薬剤師への相談:
他の西洋薬との相互作用や妊娠中・授乳中の服用について必ず確認を。 - 大黄含有処方の長期連用禁止:
防風通聖散や大柴胡湯など大黄が多い処方は2週間以内が目安。 - 体調変化の記録:
服用前後の体温、排尿回数、睡眠の質などをスマホアプリで管理すると効果を実感しやすい。 - 副作用チェック:
吐き気、下痢、発疹など異変があれば即中止し医師相談を。

















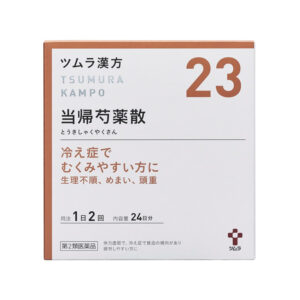


コメント